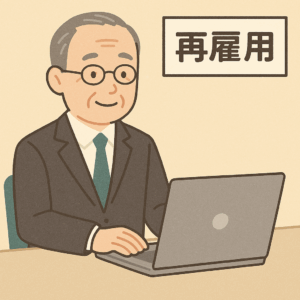「管理者を退職させない10のポイント」byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
先日UPした「ベテラン介護職員を退職させない10のポイント」を読んで友人Aから、
「管理者の退職は?」
と言われること必至と思い、食い気味に準備を進め一週間・・・
こんな時に限り、何も言ってこないとはツンデレすぎる。
と、いうことで、介護事業所の安定運営において要となる管理者。その存在は非常に大きな意味を持ちます。
ところが、業務過多・孤独感・板挟みといったストレスから、管理者が離職してしまうケースも少なくありません。
今回は、そんな管理者の離職を防ぐための具体的な10の取り組みをご紹介します。
管理者の離職防止なので、どちらかというと経営層に見てもらえたらと思います!!
目次
1.「業務の範囲と責任」を明確にする
管理者は何でも屋になりがちです。役割の線引きを明確にし、事務や現場の細かい業務は他のスタッフと分担できるよう整えることで、燃え尽きや過労を防ぐことができます。管理職に専念できる環境づくりが第一歩です。
2.「一人で抱えない」体制を構築する
判断や対応をすべて一人で行う状態は、管理者にとって大きなストレスです。副管理者やリーダー層との情報共有・役割分担を明確にし、「相談できる・任せられる」環境をつくることが離職防止につながります。
3.「上層部との定期面談」で孤立を防ぐ
経営者や法人本部と定期的に面談を設け、現場の状況や課題を共有しましょう。「困っていることが言えない」「方針のすり合わせができない」状態が続くと、管理者は疲弊して離職を選ぶ可能性が高くなります。
経営層も積極的に、管理者の状況を把握し、孤立を感じさせないようなフォローが必要です。
4.「管理職研修」で不安とストレスを軽減
現場上がりの管理者は、経営・労務・マネジメントに不安を抱えることも。外部研修や同行支援などを通じて学びの機会を提供することで、「学べる職場」「成長できる役職」としての魅力が生まれます。
また小規の法人では管理者が一人しかいないなど、管理者が孤独を感じやすい環境です。
外部研修などで、他の管理者と意見交換することで、管理者の悩みや不安を軽減できることもあります。
5.「他施設とのつながり」を持たせる
他事業所の管理者と情報交換できる場(合同会議・勉強会・LINEグループなど)があると、自分だけが悩んでいるわけではないと実感でき、メンタル面の安定にもつながります。社内外に相談先を複数持たせましょう。
6.「数字と現場」のギャップを理解してもらう
経営側からの指示が現場実態とかけ離れていると、板挟みになる管理者は大きなストレスを感じます。数値目標や方針を示すだけでなく、「現場の声」も汲み取った柔軟なやりとりが必要です。
数字は大切です。ただ数字が全ては無く、なぜその数字になったのかという、原因分析し、管理者とその対策をおこなうことが重要です。
7.「裁量の余地」を与える
管理者がただの“伝達係”になると、やりがいを失い離職の原因に。「人員配置やレイアウトの見直し」「シフト作成権限」「備品発注の決定」など、業務の中に裁量や判断権を持たせることで、自律的な働き方が可能になります。
8.成果を「数値化して評価」する仕組みを
管理職の頑張りは成果が見えづらいもの。利用率の改善や離職率の低下、職員アンケートでの満足度向上など、成果を数値で把握・共有し、評価や賞与に反映することで、やりがいと報酬のバランスを保てます。
9.「プライベートへの配慮」も忘れずに
管理者も一人の人間です。休日の急な呼び出しや業務時間外の連絡が常態化すると疲弊します。「緊急時は副管理者が対応」「夜間連絡は翌朝に」など、仕事と私生活のメリハリを意識した運用が必要です。
10.「感謝と信頼」が最大の支えになる
管理者は日々、現場・家族・法人の間で調整に奔走しています。その頑張りに対して、上司や職員から「ありがとう」「頼りにしている」といった言葉があるだけで、大きなモチベーションになります。声に出して伝えることが最も効果的です。
事業所の要である管理者!!
管理者の能力で、その事業所は良い方向にも、悪い方向に進みます。
有能な管理者が離職なんてことになると、その事業所の運営の危機といっても過言ではありません。
ついつい仕事を任せっきりになる管理者ですが、上司や経営層は常に管理者への配慮は必要ですね。
以上