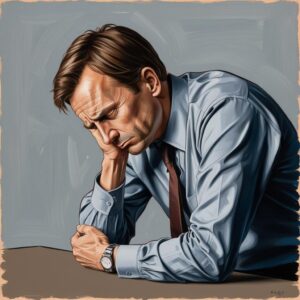「年次有給休暇のあれこれ」について。byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所@横浜の正躰です。
お客様のとある質問からドツボにはまっている今日ですが・・・その質問とは
「有給単価を計算する際に、固定残業手当を支給している職員の場合、どのように計算するの?」
と、いうもので、経験豊富な社労士ならサクサクと回答するのでしょうが、
新進気鋭の社労士(経験不足の社労士・・・)としては、即座の回答に窮してしまったもので、
自戒の念を込めて、ここにこの場合の有給の取扱を記します・・・
そのまえに、まず有給について基本に立ち返ると、
年次有給休暇とは
労働者が「給料をもらいながら休める」法律上の権利です。
条件を満たせば、会社の許可がなくても休むことができ、給料は全額支払われます。
年次有給休暇がもらえる条件とは?
原則は以下の 2つの条件 を満たしたとき、年休の権利が発生します。
・初回は入社から6か月間継続して働いたこと(2回目以降は初回付与から1年後)
・その間の出勤率が8割以上あること
付与される日数(週5日勤務の正社員の場合)
| 勤続年数 | 有給日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
※パートタイム勤務の場合は、勤務日数に応じて比例的に付与されます。
詳細は以下、厚生労働省のリーフレット参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
有給休暇の特徴とルール
・繰り越し:有休は 2年間有効。未使用分は翌年に繰り越されますが、2年で消滅します。
・取得の申請:原則として、労働者が「いつ休むか」を決められます。会社は「業務に支障がある場合のみ」別の日に
変更できます(これを「時季変更権」といいますが、変更権の行使は認められない場合が多いです)。
・拒否は原則NG:理由を言わなくても取得可能。会社は基本的に拒否できません。
義務化された「年5日の取得」
2019年から、年休が10日以上付与される労働者には、年5日の有休取得が義務になりました(会社側の責任です)。
取得させなかった場合は、会社に罰則(30万円以下の罰金)があります。
半日・時間単位の取得
・半日単位:法律上はOK。会社が認めれば可能です。
・時間単位:会社が就業規則などで認めていれば、年間5日まで可能です
などが、労働者側にとっては一般的なルールかと思います。
もっと詳しく知りたい方は厚生労働省のリーフレット参照ください。(上記URLと同じもの)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
有給休暇取得時における固定残業手当の取扱
さて、本題に戻り、では
「有給単価を計算する際に、固定残業手当を支給している職員の場合、どのように計算するの?」
についてですが、まずは有給休暇取得日の賃金は「通常の賃金」、つまり出勤していれば支払われるはずの賃金を支給する必要があります。
この場合、固定残業手当についても通常支払われる賃金の一部として取り扱います。
すなわち、固定残業手当は、残業の有無にかかわらず支給する性質のものであるため、有給休暇取得日にも通常通り支給するのが原則となるのです。
なお、就業規則に固定残業手当について欠勤控除の定めがある場合でも、有給休暇は欠勤ではないため、控除の対象とはなりません。
残業といえども、固定残業代は通常の手当と同じ取扱をして、有休取得時の計算の基礎に含める必要があると言うことですね!!
その他、疑問や質問、また労務関係のお悩みがございましたら、
ディライト社会保険労務士事務所へお問い合わせください。
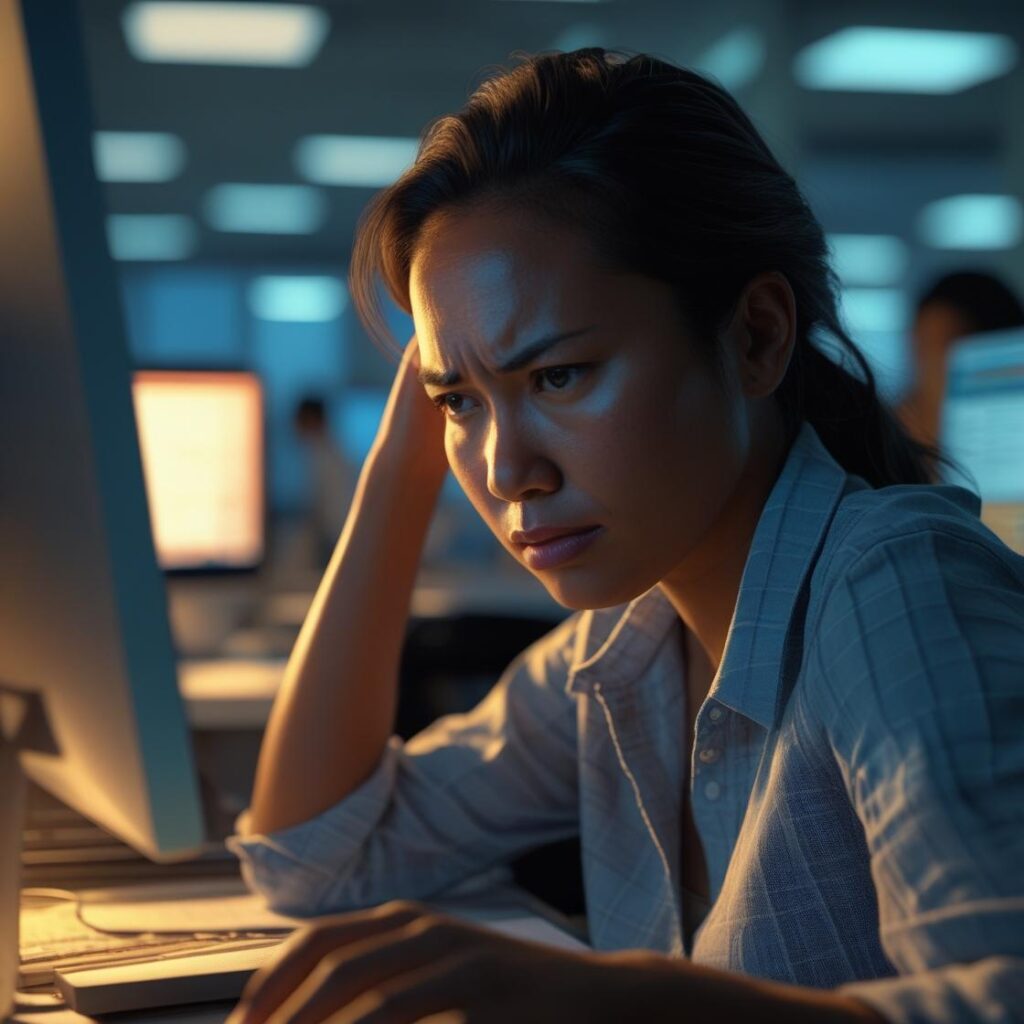
以上