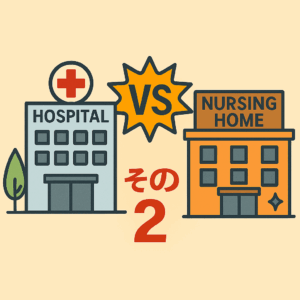「医療と介護の連携、5つの壁と乗り越え方|医療法人運営の介護施設がすべきこと その1」byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
先日、以前の職場の同僚と食事をして、
その際に医療法人の運営する介護施設だからこそ起こりうる問題点について話あってみました。
その際の内容!!医療法人の運営する介護施設だからこそ起こりうる問題点とその対策方法(その1)について、
まとめてみたので記載してみます。
1.情報共有の不足・非効率性
【問題点】
医師や看護師などの医療職と、介護福祉士やケアマネージャーなどの介護職との間で、利用者の日々の状態変化やケアに関する情報がスムーズに共有されないことがあります。例えば、「医療側からの指示が介護現場に正確に伝わらない」「介護現場で発見した利用者の細かな変化(食欲不振、微熱など)が医療側に迅速にフィードバックされない」といった問題です。これにより、対応の遅れやケアの質の低下を招く可能性があります。
【解決策】
ICT(情報通信技術)ツールの導入・連携強化:
電子カルテと介護記録システムを連携させ、双方がリアルタイムで情報を閲覧・入力できるようにします。
スマートフォンやタブレットで利用できるチャットツールを導入し、職種間の報告・連絡・相談を円滑化することも有効です。
多職種カンファレンスの定例化:
医師、看護師、介護職員、リハビリ専門職などが定期的に集まり、利用者一人ひとりの状態やケア方針について議論する場を設けます。顔を合わせて対話することで、記録だけでは伝わらないニュアンスや情報を補完し、チームとしての一体感を醸成します。
2.職種間の役割分担の曖昧さ
【問題点】
医療行為と介護(生活支援)行為の境界線が曖昧な場面で、介護職員が「どこまで対応して良いのか」と判断に迷うケースがあります。例えば、褥瘡(床ずれ)の処置やインスリン注射後の観察、経管栄養の管理など、医療的な判断が求められる場面で、責任の所在が不明確になりがちです。これにより、介護職員が過度な負担や不安を感じたり、必要な処置が遅れたりするリスクがあります。
【解決策】
役割分担マニュアルの作成と周知徹底:
具体的なケースを想定し、「これは看護師の業務」「これは研修を受けた介護職員でも対応可能」といったように、職務権限と役割分担を明確にしたマニュアルを作成・共有します。
緊急時対応フローの整備:
急変時や判断に迷う際の連絡体制や報告ルートを明確にしたフローチャートを作成し、全職員がいつでも確認できるようにします。定期的な研修やシミュレーションを通じて、フローに沿った行動がとれるように訓練することも重要です。
3.専門性の違いによる価値観の対立
【問題点】
医療職は「治療」や「生命維持」を最優先に考える傾向があるのに対し、介護職は利用者の「生活の質(QOL)」や「その人らしさ」を重視する傾向があります。この価値観の違いから、ケアプランの方針(例:食事制限の厳格さ、リハビリの強度など)を巡って意見が対立し、連携がうまくいかなくなることがあります。
【解決策】
多職種連携教育(IPE)の実施:
合同研修会などを通じて、お互いの専門性や業務内容、価値観について理解を深める機会を設けます。相手の立場を尊重し、専門家として対等な関係を築く文化を醸成します。
利用者中心の共通目標の設定:
利用者やその家族の意向を最大限に尊重し、「穏やかに過ごしたい」「最期まで口から食事を楽しみたい」といった利用者本人の希望をチーム全体の共通目標として設定します。その目標達成のために、各専門職がそれぞれの立場から何ができるかを考え、協力し合う体制を構築します。
4.高度な医療ニーズへの対応力不足
【問題点】
近年、介護施設に入所する高齢者は、看取り(ターミナルケア)や認知症の周辺症状(BPSD)、複数の慢性疾患を抱えるなど、医療ニーズが非常に高くなっています。特に夜間帯など医療スタッフが手薄になる時間帯に、介護職員だけでは対応が困難な状況が発生しやすくなっています。
【解決策】
介護職員への医療的ケア研修の推進:
喀痰吸引や経管栄養など、法律で認められている範囲で介護職員が実施できる医療的ケアの研修を積極的に行い、対応可能な人材を育成・増員します。
オンコール体制の強化と訪問診療との連携:
夜間や休日でも、看護師や医師にすぐに連絡がつき、的確な指示を受けられるオンコール体制を整備・強化します。また、専門的な医療が必要な場合は、地域の訪問診療医や専門医とスムーズに連携できる体制を構築しておくことが重要です。
5.医療保険と介護保険制度の複雑さ
【問題点】
利用者が受けるサービスによっては、医療保険と介護保険のどちらを適用するのか、あるいは両方をどのように使い分けるのかといった判断が非常に複雑です。例えば、訪問看護やリハビリテーションなどが該当します。この制度の複雑さが、請求業務(レセプト業務)の煩雑化を招き、事務スタッフの大きな負担となっています。算定ミスは、法人の経営にも直接影響を与えます。
【解決策】
専門知識を持つ事務スタッフの育成・配置:
医療保険・介護保険の両方の制度に精通した事務スタッフを育成し、専門部署を設置する、あるいは外部の専門家と顧問契約を結ぶなどの対策を講じます。
請求業務支援システムの導入:
医療用のレセプトコンピュータと介護保険請求ソフトが連携できるシステムを導入することで、二重入力の手間を省き、請求業務の効率化と算定ミスの防止を図ります。
医療法人が運営する介護施設と言っても、訪問系、施設系、通所系多岐にわたるので、全てが当てはまる訳では無いと思いますが、先日の話の中ではこのような事が問題点として上がりました。
後日その2も掲載予定です!!
もし上記のような問題点に直面されている経営者様、担当者様。
お気軽にディライト社会保険労務士事務所へご相談ください。
以上