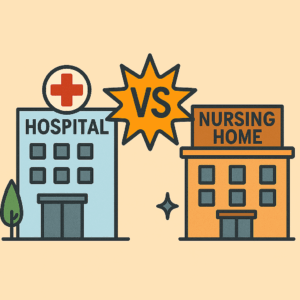「医療と介護の連携、5つの壁と乗り越え方|医療法人運営の介護施設がすべきこと その2」byケアマネ社労士@横浜
みなさんこんにちは。ディライト社会保険労務士事務所の正躰です。
前回は、以前の職場の同僚と食事をして、医療法人の運営する介護施設だからこそ起こりうる問題について
5つ挙げてみました。本日はその際に話しが出たもう5つをご紹介してみます。
前回同様、問題点&解決策形式で記載してます。
1.医療主導のヒエラルキーによるコミュニケーション不全
【問題点】
医療法人特有の、医師を頂点とする階層構造(ヒエラルキー)が介護現場にも持ち込まれ、介護職員が医療職に対して意見を言いづらい、または意見が軽視される雰囲気があるケースです。これにより、介護現場で発見された利用者の重要な変化や、ケアに関する建設的な提案が上がりにくくなり、チーム全体のパフォーマンス低下や、職員の心理的安全性が損なわれる原因となります。
【解決策】
フラットなコミュニケーションを促す仕組みの導入:
職種や役職に関わらず対等な立場で意見交換を行う「ラウンドテーブルミーティング」などを定期的に開催します。また、心理的な壁を感じる職員のために、匿名で意見や提案を投稿できるデジタル目安箱などを設置することも有効です。
管理職へのリーダーシップ研修の実施:
医師や看護師長などの管理職を対象に、部下の意見を引き出すための傾聴スキルや、会議を円滑に進めるファシリテーション能力を高める研修を実施し、風通しの良い組織文化を醸成します。
2.人事評価・待遇における職種間格差
【問題点】
医療専門職(医師、看護師など)と介護専門職(介護福祉士など)との間で、給与体系や手当、昇進の機会などに格差が存在することが少なくありません。この格差が、介護職員のモチベーション低下や不公平感につながり、優秀な人材の離職や採用難を招く一因となっています。
【解決策】
職務評価制度の導入と見直し:
専門性、業務の難易度、責任の重さ、精神的・肉体的負担などを多角的に評価する共通の職務評価制度を導入します。これにより、職種の違いによらず、職務の価値に基づいた公平な給与体系を構築します。
キャリアパスの複線化と明示:
介護職にも、現場の専門性を極める「スペシャリストコース」や、管理職を目指す「マネジメントコース」など、多様なキャリアパスを整備・明示します。これにより、介護職員が長期的な目標を持って働き続けられる環境を整えます。
3.経営方針における医療と介護の視点のズレ
【問題点】
医療法人の経営陣が、病院経営の視点や成功体験をもとに介護施設を運営しようとし、介護保険制度の収益構造や、「生活の場」としての施設の特性への理解が不足している場合があります。その結果、現場の実態にそぐわないコスト削減策や、医療的ケアに偏重した非効率な運営方針が打ち出され、現場が混乱することがあります。
特にベテラン看護師の発言力がなぜかまかり通るなど往々にしてあります。
【解決策】
介護部門の経営への参画:
介護施設の管理者や現場リーダーを法人の経営会議に定期的に参加させ、現場の視点や介護保険事業の特性を経営判断に反映させる機会を設けます。
介護施設に最適化されたKPIの設定と共有:
医療機関とは異なる、介護施設に適したKPI(重要業績評価指標)、例えば「入居率」「職員定着率」「家族満足度」「ADL維持・改善率」などを設定し、法人全体でその数値を共有し、目標達成に向けて取り組みます。
4.利用者・家族への説明の不統一とそれに伴う混乱
【問題点】
利用者の状態について、医師からは医学的見地(病名、予後など)からの説明が、介護職員からは生活場面での様子(食事量、活動状況など)が別々に行われることがあります。その際に両者の情報に食い違いや温度差があると、利用者や家族が「どちらの言うことが正しいのか」と混乱し、施設全体への不信感につながるリスクがあります。
【解決策】
多職種合同でのインフォームド・コンセントの実施:
重要な方針決定や病状説明の際には、医師、看護師、担当介護職員、ケアマネージャーなどが同席し、チームとして統一された見解を家族に伝える「合同カンファレンス」の場を設けます。
情報共有ツールの一元化:
医療・介護の両面からの日々の様子や連絡事項を、一つのツール(連絡ノートや専用アプリなど)に集約して記録・共有します。これにより、家族は一元的に情報を得られ、職員間の認識のズレも防ぎます。
5.終末期ケア(看取り)における意思決定プロセスの対立
【問題点】
人生の最終段階におけるケアの方針を決定する際、「医学的に可能な限りの延命措置を」と考える医療的視点と、「本人の苦痛を緩和し、その人らしい最期を」と考える介護的視点が衝突することがあります。この意思決定プロセスが施設内で標準化されていないと、職員間で対立が生まれたり、利用者や家族の本当の意向が十分に尊重されないまま方針が決定されたりする危険性があります。
【解決策】
ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の推進:
利用者が心身ともに安定しているうちから、本人や家族と多職種チームが「もしも」の時の医療・ケアに関する意向を繰り返し話し合い、共有・記録しておくプロセス(ACP)を施設全体で推進し、文化として定着させます。
倫理カンファレンスの定例化:
方針決定が困難な事例について、多職種で倫理的な側面から検討する「倫理カンファレンス」を定期的に開催します。必要に応じて外部の専門家(弁護士や臨床倫理士など)の助言を求めることで、客観的かつ多角的な視点から最善の方策を探ります。
如何でしょうか。全てでは無くとも一つ、二つは当てはまる事があるのではないでしょうか。
もし上記のような問題点に直面されている経営者様、担当者様。
お気軽にディライト社会保険労務士事務所へご相談ください。
以上